光合成の研究とは?
2012/3/25更新
多岐にわたる光合成研究
光合成の研究の歴史は非常に古く,プリーストリーによる酸素の発見(1772年)までさかのぼることが出来ます.その後,植物生理学・生化学の一分野として発展し続け,現在ではこの分野にとどまらず,生態学や分類・系統学,さらには物理学や化学,農学や工学の研究者も光合成の機能に着目し,研究を進めています.
光合成とは?
光合成は小学校の教科書にも出てくるほど重要な機能で,ポケモンにも登場する(くさポケモン)など大人から子どもまで,幅広い方になじみのある言葉でしょう.この光合成は,シアノバクテリア(正確にはシアノバクテリアは細菌の仲間です)も含めたいわゆる「植物」が行う,地球上最大の化学反応と言えます.ヒトをはじめ,地球上で酸素を必要とする生物は,すべて植物の光合成により生産された酸素を利用しています.
では,「光合成について述べなさい」と問われたらどうでしょう.大部分の方は,「太陽からの光エネルギーを使って,二酸化炭素と水から有機物を合成し,酸素を発生する働き」と答えると思います.正解です.ただ,これは出発と終点を述べているだけなので,その途中がありません.実はその途中の過程こそが,光合成では重要です.なぜなら,生物の仕組みの中でこれだけ精巧に出来ている仕組みが他になく,さまざまな環境要因により影響を受けるからです.たとえば,光合成では必ず光を必要としますが,あまりにも強すぎると,光を受け取って化学エネルギーに変換する仕組み(光化学系)が壊れてしまうことが知られています.これは,活性酸素の仕業であることがわかっています.また,温度も重要な要因です.温度が低ければ有機物の合成を行うための仕組み(酵素反応)がうまく働きません.高等植物は移動することができないので,体内の様々な機能をおかれた環境にあわせてこれらを最適化する仕組みを持っています.光合成の概略は下図のようになりますが,葉緑体のチラコイド膜に埋め込まれた大きな複合体で,光エネルギーが化学エネルギーに変換され,ストロマの部分で二酸化炭素の固定,すなわち有機物の生成が行われます.
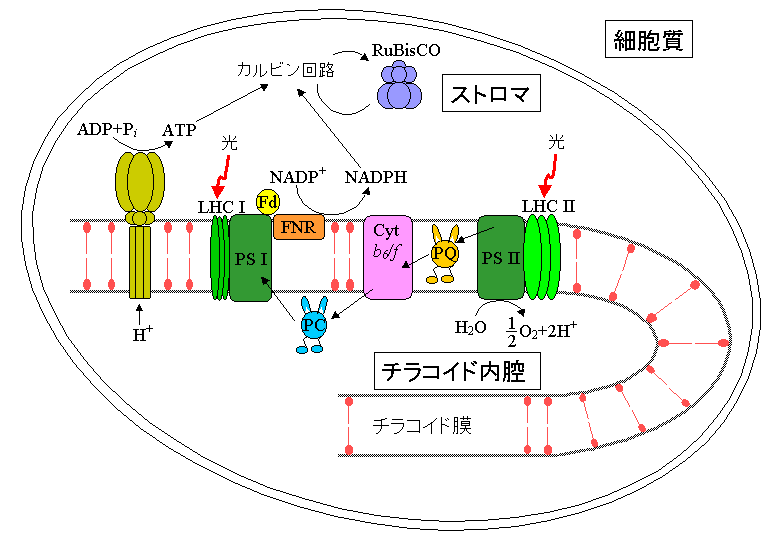
光合成研究の魅力
なぜ,光合成はこんなにも多岐にわたる研究者により,研究されているのでしょうか?理由はいくつかあると思いますが,(僕なりに考えると)そのひとつは光合成生物の誕生が,生命の歴史において非常に重大な出来事を引き起こしたからです.それは,約30億年前に出現したといわれる酸素発生型の光合成生物,すなわちシアノバクテリア(ラン藻,藍色細菌)の存在です.シアノバクテリアの登場により,これまで大気中にほとんど存在しなかった酸素が爆発的に増加し,還元型物質を酸化したり,大気中にオゾン層を形成して紫外線の陸上への到達をかなり弱めました.その結果,生物は陸上に進出できるようになり,生物相の多様化が進みました.
もうひとつの理由は,光化学反応に温度依存性がみられないことです.通常の物理化学的反応は,液体窒素温度では分子運動が停止し,化学反応は起きません.ところが光化学反応では液体窒素温度(-196℃, 77K)どころか,もっと低温の4K(極低温といいます)でも反応が進行します.これは量子物理学のトンネル効果によるものですが,このような物理化学的な常識を覆すような仕組みが,さまざまな領域の人たちを魅了するのでしょう.ちなみに,低温下では分子の運動が抑制される分,種々の測定においてよりシャープな結果が期待できます.
ちょっと余談
講義というのは,面白いと思っていても,いつの間にか眠くなるもので,僕もそうでした.生物系の学生さんは物理化学領域に話がおよぶと眠くなってしまうようです.それは仕方がありませんね.ところが同じ話をしても,生態学の領域と絡めた話をすると,そんなに眠くはならないようです.
上にも書きましたように,たくさんの研究者により光合成の研究が行われ,複合体を構成しているタンパク質の種類などは詳細がわかってきました.そのため残念ながら,専門外の人たちばかりか,内部の人からも「もう光合成の研究は終わった」という声を耳にすることがあります.
終わらない研究
つい最近,酸素発生を行う光化学系IIの構造がわかりました.しかしこれで光合成研究が終わったわけではなく,あくまでも個々の選手がわかってきたところです.したがって光合成の研究は終わるどころか,今後さらなる解析が必要となってきました.また,どのような進化的過程を経てシアノバクテリアが誕生したのかは未だにわかりません.それに次から次へと新しいことがわかってきています.例えば,クロロフィルaやbではなく,クロロフィルdや,亜鉛(Zn)が中心金属であるバクテリオクロロフィルをもつ光合成細菌が見つかりました.さらにごく最近,クロロフィルfというのも見つかりました.また,カラカラに干からびていても,水を加えるだけで光合成機能が回復するシアノバクテリアや地衣類に共生している藻類(緑藻類の一部やシアノバクテリア)がいます.これらの発見は既存の光合成の常識をぶち壊すには十分です.さらに藻類と陸上植物では光環境がまったく違いますし,陸上植物でも草本類と木本類(いわゆる樹木)では,基本的なメカニズムは同じでも,光合成系をその光環境に合わせて効率化する仕組みは,植物により異なります.これらの解明はまったく行われていません.
これからの光合成研究
これからの光合成研究は,植物を取り巻く光環境や温度環境に対して,個々の植物がどのように応答するのかを調べる研究や,さらにもっとマクロなレベル,すなわち地球環境変動も視野に入れた研究が必要になってきています.光合成の研究に興味がある大学生や高校生・中学生の皆さんは,得意な領域からアプローチしてみてはいかがでしょうか?物理が得意なら分光測定などから,化学が得意ならタンパク質の解析から,遺伝子に興味があれば分子生物学から,生態学に興味があれば物質生産などの面から,コンピューターに興味があれば環境変動のシミュレーション解析や人工衛星画像を使った光合成生産量の解析の面から.さらに工学的な分野なら人工光合成の研究も活発になっていますし,農学なら作物生理や育種の面から.どこからでも大歓迎です.